morinosカフェVol.20 「根の上高原発:自然と人をつなぐ活動から見えてきたこと」を開催しました
開催した日:
20回目を迎えたmorinosカフェ。ゲストを迎えてざっくばらんに話す交流の場です。
今回は中津川市根の上高原在住で「NENO自然体験合同会社」という自然体験事業所を運営している「あかぽん」こと、赤尾友和さんをゲストに迎えました。雪が積もる2月7日(金)の夕方、8名が参加しました。

前半は赤尾さんから、自身のこれまでの歩みと今回のテーマである、「自然と人をつなぐ活動から見えてきたこと」について話していただきました。
冒頭、「ライフラインチャート」と題して、生まれてから現在まで、赤尾さん自身の感覚による人生のアップダウンを紹介していただきました。
両親が根の上高原に開いたユースホステルを経営しており、そこで生まれ育った赤尾さん。物心つく頃は、常に多くの若者(ユースホステル利用者)に囲まれており、5歳の時に受けた知能テストでは、全国でもトップクラスの成績だったそう。(この時が人生のピークだったと、笑いながら紹介していただきました)
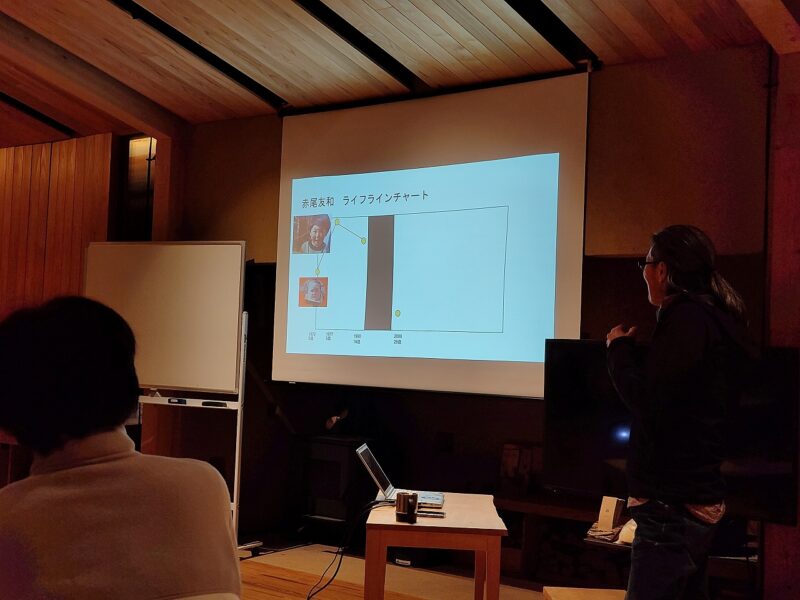
進学・就職を含め、悩んでいた20代は「暗黒時代」と紹介していましたが、転機となったのは28歳の時。「自然の中で過ごしたい」と思うようになり、地元根の上高原に戻り30歳となった2002年、「あすなろヴィレッジ」という少人数での子どもキャンプを始めました。屋号として使っている「NENO」は、「Nakatsugawa Ena Nature Office(中津川・恵那自然事務所)」の頭文字で、根の上高原の「根の」でもあり、2025年に法人化しました。
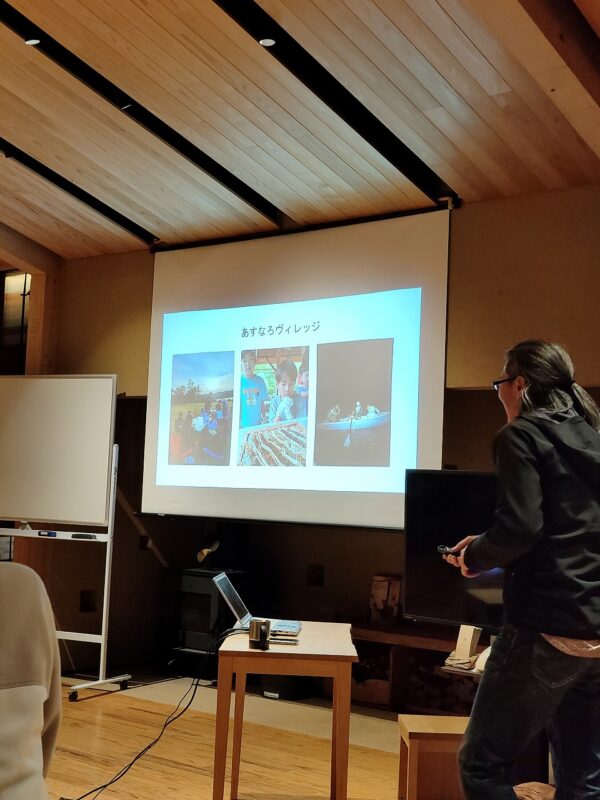
あすなろヴィレッジ以降、学校や企業等を対象とした宿泊研修の受入や、地元の子どもを対象とした森林体験学習、幼児を対象とした「やまっこさんぽ」、大人や親子を対象とした自然体験アクティビティ等、幅広い活動を展開するようになりました。
最近では、行政からの受託事業に加えて、地域資源を活かした取り組み(例:東濃名物「栗きんとん」の製造体験、山伏の体験等)も行っているそうです。
赤尾さんが活動を始めた背景には、社会に対する憤りや、自分で考える・決める・満足する・諦めるといった「自己決定」を大切にしたいという思いがありました。
「それぞれが、それぞれで活きればいい。周りも一緒なら、なおいい。」と赤尾さんは言います。そして、自分の両親が始め、自身が20年以上に亘って受け継いできた、この根の上高原の雰囲気を保ちたいと願っています。そのために、「いい風景があるから移住するのではなく、一緒にいい風景を創っていく=当事者になる」という気持ちを持ってほしいと。
最後に、NENOの活動を通して今思うことと題して、いくつかのキーワードを提示していただきました。その中に「ANTI-morinos」という気になるワードがあったので、その意味を聞くと、
「morinosができるって、2020年の正月の新聞に載っているのを読んだんです。岐阜県が多額の資金を投じて自然体験の拠点を整備するんだと。これは自分の仕事がなくなるかも…と思ったんです。正直、妬みや羨ましいという気持ちもありました。でも、morinosが正統派だとすると、NENOは野武士のような存在。morinosのやってることが正解、morinosの真似をしておけば大丈夫と、試行や工夫をやめてしまう他地域の自然体験関係者の風潮に対してのアンチテーゼなんです。本流としてmorinosの動向をみながら、学び、刺激を受けながら、じゃあ各自、各地域はどのように特色を出して自然体験を盛り上げて行くのか。それぞれが考えて工夫しなくては、発展はないのではと思っています。」
とコメントしていただきました。

赤尾さんの話は尽きないのですが、いったん区切って、参加者同士で感想や、赤尾さんへの質問を共有しました。
最後に参加者から出された質問に赤尾さんから答えていただきました。
※質疑の要旨は以下の通り。
Q1 どうやって稼いでいるのか?
A1 これまで補助金を使わなかった。稼ぐ工夫を常にしている。それまで値段がつけられていなかった自然体験に値付けをしてきたと思う。
Q2 後継を育てるつもりはあるか?
A2 2025年に法人化した。これは税制面などを考えてのこともあるが、1つにはNENOをやりたいといった人が現れた時に、引き継げるようにしておきたいという思いもある。
Q3 地元の行政とどのように関係性を作っていったのか?
A3 活動を始めて10年位経った頃、周りが認めてくれるようになったと感じている。時間がかかる。行政に対してはあまり主張しないほうが良い。反対して対立するのではなく、求められていることに応えることが大切では。
Q4 AI(人工知能)が急速に広がる現代で、私たちはどのように自然との関わりを保つべきか?
A4 自分が苦手だというのもあるが、NENOはAIやデジタル技術を取り入れず、アナログでいこうと考えている。なぜなら、必ずAIやデジタルに対する反動があると思うので。
Q5 モチベーションを維持するには?
A5 アイデアはたくさん出る。でも100個アイデアが出ても、実現できるのは1個くらい。我流でこれまでやってきたが、周りに助けてもらってきたと感じている。
Q6 子どもは今も昔も変わっていないとのコメントにはその通りだと思う。では親にはどのような働きかけが必要か?
A6 親は子どもをもっと放っておけばよい。今は情報が多すぎて「~すべき」「~しなければならない」が多すぎる。
赤尾さんとのやり取りは終了後も続きました。参加者一人一人の胸に、赤尾さんのメッセージは届いたのではないでしょうか。
【参加者の声】(アンケートより一部抜粋)
・人との出会いや繋がり縁、そしてタイミングを逃さない嗅覚みたいなものが大事だなぁと思ったのと、ポリシーを持ってやり続ける事が大切だなぁと思いました。
・いいところだから移住するのではなく、いいところにするため一緒に創っていくという気持ちがないと続かないというのは、確かに!と思いました。赤尾さんは不思議な魅力がありますね。
報告者:大武圭介(ウォーリー)ホールアース自然学校

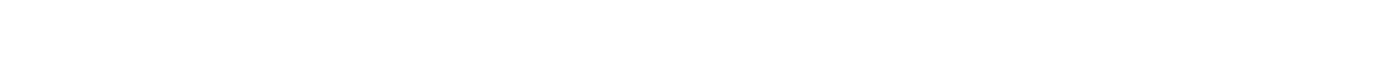
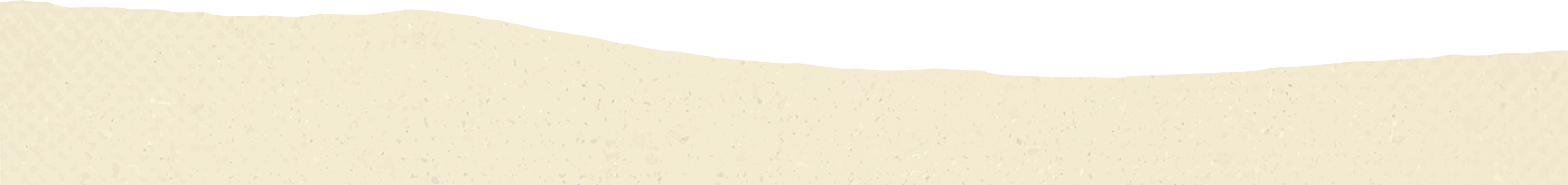

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)
Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529







