「地域に根差した森林活用プロデューサーって何だ?-伊豆市またね自然学校の取り組み」を実施しました
開催した日:
真冬とは思えない暖かさとなった1月23日(木)、「地域に根差した森林活用プロデューサーって何だ?-伊豆市またね自然学校の取り組み」を実施しました。ゲストは、静岡県伊豆市で活動する「またね自然学校」の斉藤大輔さん(ニックネーム:だいちゃん)と竹夏さん(ニックネーム:たんたん)。岐阜県内各地から成人16名が参加しました。

またね自然学校のたんたん(左)、だいちゃん(中央)、カナメ(右・サポートスタッフ)
最初にたんたんから、またね自然学校の取り組みを紹介していただきました。伊豆半島のほぼ中央に位置する、伊豆市中伊豆町に拠点を構えるまたね自然学校は、だいちゃん・たんたん夫婦によって2019年4月に創業。団体の理念として「四季を感じ楽しむ 日本文化に根ざした 豊かな暮らしのお裾分け」を掲げています。また、前職の自然学校で学んだ「インタープリテーション」という手法を取り入れ、体験するだけでなく、そこからの気づきや学びを重視する、環境教育に取り組んでいます。
2020年からは行政からの受託事業として、地元伊豆市の地域学習に取り組み始めました。しかしこの年、コロナ禍が起こってあらゆる事業に制限がかかるようになりました。狭い室内だけでは先が見通せないと、新たな拠点探しを始めました。
2021年、現在のまたね村がある、30年以上放置された廃ペンションを見つけ、拠点としての再整備を始めました。高さ3mを超える灌木に覆われた廃ペンションとその周辺を整備するのは並大抵のことでなく、のべ500名を超えるボランティアが関わりました。


整備を始めた当初の様子(上)と、整備後の様子(下)
2022年、伊豆市の森林環境譲与税を活用した、地元中学校等に対する森林・林業体験事業にも取り組み始めました。そして2024年、多くの人々の協力・支援を得てついに新たな拠点「みんなのいえ」が完成し、オープニングには伊豆市長もかけつけてくれたそうです。
たんたんからは、主催事業のキャンプに参加した引きこもりの子どもが、キャンプの最後に「生かされていることに気づかされた」と言って、積極的な姿勢に変わったというエピソードが紹介され、自分たちがやっている事業の手応えを感じたとのこと。
たんたんからのプレゼンテーションが終わった後、3-4人で自己紹介をして感想や質問を共有しました。初対面の参加者もおり、自身の活動紹介や抱えている悩みなどに話題は広がり、「もっと話したい」という声も聞かれました。

後半は、伊豆市で捕獲した鹿革を使ったクラフト体験を行いました。
最初に猟師でもあるだいちゃんから、シカの現状や問題について紙芝居で解説していただきました。伊豆半島ではニホンジカが増えて農林業への食害が増えており、狩猟を行っているそうです。今回使う鹿革はすべて自分たちが捕獲したシカで、肉をいただいた後の皮を、なめし業者に依頼して革にしたものです。


色とりどりに染色された鹿革ですが、よく見ると小さな傷や穴が開いているものが。タンタンによると、これらは人間に管理されていない野生の証拠で、マダニに吸血されたり、シカ同士争ってできた傷だそう。参加者はそれぞれの鹿革をじっくり見ながら、デザインを考え、フレームづくりに取り掛かりました。

型紙にデザインを描き、それを革に写してカッターナイフで切ってボンドで台に貼り付けました。シンプルですが、鹿革が薄く伸びやすいためピッタリ貼るにはコツがいります。1時間ほどで、それぞれ違うデザインでカラフルなフレームが完成しました。



完成後たんたんから、「鹿革は日本で古くから使われてきた素材で、日本の風土にぴったりマッチしている。愛着を持って作ったものを使い切ることがSDGsにつながるのではないか。」と話していただきました。

最後に参加者から出た質問への回答を、二人からしてもらいました。
【質疑応答の要旨】
Q1.地域や地元との付き合い方のコツは?
A1.まずは断らない。お誘いには基本参加する。地元の方が多く利用する共同浴場があるのだが、そういう場に積極的に言って裸の付き合いもしている。
Q2.スタッフの役割分担はどうしているのか。
A2.スタッフは得意分野を持った人を、適材適所で関わってもらっている。代表の2人については、だいちゃんは慎重派、たんたんは開拓者精神で「まずやってみよう」と正反対。互いに違うからバランスが取れるのでは。
Q3.またね自然学校の経営について、資金調達はどのように行っているのか。
A3.移住当初、たんたんは地域おこし協力隊として収入を得ており、だいちゃんは地元の林業会社で働いて現金収入を得ていた。またね村の改修工事では、苦労したが国からの補助金を得ることができ、より信頼を得られるようになった。加えて、クラウドファンディングにチャレンジして資金を得た。
Q4.行政や他の事業者とうまくやるコツは?
A4.自己完結しようとせず、出来るだけ地域の協力・知恵を取り入れ一緒に取り組む事を心掛けている。
Q5,どうやって広報・集客しているのか。リピーターが多いとかえって新規参加者が入りづらいのでは。
A5.圧倒的にリピーターが多く、リピーターからの口コミも多い。一方で、新規参加者が孤立しないよう、全てのイベントにおいてリピーターだけで固まらない様に意識的に分散させる。また、初めて参加した方が発言しやすい環境づくりをスタッフ全員が心掛けている。
質問に答えた後、だいちゃんから「結局最後は愛だと思うんです。ちょっとクサイ言葉だけど。突き詰めていくと、人への想いがないとできないのでは。今日、私たちの話を聞いて愛を感じた方は、是非伊豆へ来てください。待っています。」と熱いメッセージをいただきました。
今回、都合がつかずに残念ながら参加できなかった、伊豆市役所地域づくり課(またね自然学校の窓口)担当者からは、
「様々な地域の発展に対し、行政も民間もないと思います。一番大切なのは人と人との信頼関係。私はmata-neさんとその関係を築くことができたからこそ『闇スタッフ』とも呼んでもらえるし、市長以下幹部職員に対しても胸を張って人物紹介や、事業紹介をすることができています。これは、結果として地域活性化や地方創生につながります。」というコメントをいただきました。
森林空間活用の取り組みを本格的に始めようとしている参加者の皆さんに、またね自然学校の斉藤夫妻のメッセージは強く響いたのではと感じました。
【参加者の声】※アンケートより
・地域との交流の中でどんな事も断らないという事だったが、自分たちがやりたいことを受け入れてもらうための努力が凄いなと。けどすごく大事な事に気づかせてもらいました。やっぱり最後は愛ですね!
・森林の活用のあり方や、環境教育の進め方などなどいろいろ参考になる事が多く、発想が広がりました。実際の場に子どもを連れて行って一緒に体験したいと感じました。
・地域との繋がりを大切にしながら、事業として成り立っていることが素晴らしいなと思いました。ご夫婦の人柄も素敵でした。
報告者:大武圭介(ウォーリー)ホールアース自然学校

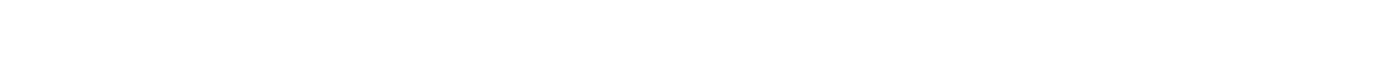
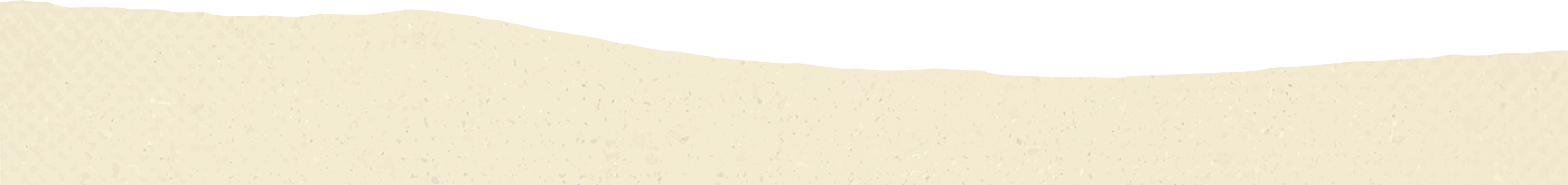

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)
Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529







