高山市清見保育園で森の出前体験~里山の恵みを感じる~
開催した日:
木々の色づきに秋の深まりを感じる季節となりました。先日morinosスタッフは高山市清見町の『清見保育園』に森の出前体験に行き、年長児18名と活動してきました。
今回のメインの活動は里山の自然の恵みを使った「焚火」。集めた枝や落ち葉を使い自分たちで火をおこし、自分たちが育てたお米と、秋の味覚であるぎんなん、栗、くるみを味わいました。
-800x600.jpg)
今日はマッチに挑戦することを伝える
はじめに火が燃えるしくみについて話をしました。火が燃えるためには①燃えるもの②熱③酸素の3つの要素が必要です。ひとつでもかけると、火はつきません。この3つの要素を加えたり減らしたりすることで火をコントロールできるのです。
-800x600.jpg)
燃えるものを運ぶ
-800x600.jpg)
焚き付けを選ぶ
話を聞き終えた子どもたちはさっそく、焚火台に燃えるものを載せていきます。子どもたちが持ってきたものの中には「すぐに燃えるもの」と「燃えにくいもの」がありました。今日の燃えるものは事前に子どもたちと先生が集めた杉の葉、樹皮、枝、地域の方からいただいた端材。どうしたら、うまく燃えるだろうかと頭を悩ませる様子もありました。
-800x599.jpg)
焚火台の準備はバッチリ
焚火台の準備ができると、いよいよ子どもたちはマッチ着火に挑戦!「家が薪ストーブだから、家族と一緒にやったことがあるよ」という子もいれば、初めてマッチを擦る子も。恐る恐るの子もいましたが、先生や友達の励ましがあり、みごと全員が挑戦し、火がつきました。
-600x800.jpg)
マッチの火付けはドキドキする
杉の葉っぱを入れると、火が大きくなることに気づいた子どもたちは、いろいろな太さの端材を火に入れ、これはどうなるかな?あれはどうかな?と試す姿がありました。
-800x600.jpg)
火ってあったかいね~
火が安定してきたら、鉄板を用意し、秋の恵みをいただくことに。
-800x600.jpg)
ポップライス作り
-800x600.jpg)
殻つきのお米が大変身!
殻つきのお米を炒ると、お米の中の水分が膨れて籾をやぶってポン、ポンと破裂。ポップコーンのようにはじけ、子どもたちが育てたお米はポップライスに大変身。軽く塩味で味付けし、みんな「おいしい」と喜んでくれました。
また、今回はぎんなん、栗、くるみを炒って食べてみることにしました。木の実を遊びに使うことはあっても、食べたことがないという子どもがほとんど。鉄板の上でコロコロ転がしてると香ばしいにおいが広がってきて興味津々。
-800x600.jpg)
ぎんなんを炒る
スタッフがメタルマッチを使ってお湯を沸かすための火をつけようとしていると、子どもたちが近づいてきました。メタルマッチは、マグネシウム合金の棒を専用のへらで削り、火花を発生させます。火花が散る様子に「すごい」と歓声が上がりました。災害時やアウトドアで便利な道具なので、こんな方法で火をつけることもできるよと紹介しました。
-800x600.jpg)
メタルマッチに見入る
-800x600.jpg)
ケトルを使ってお湯を沸かす
自分たちが育てたお米の味わい方はポップライスだけではありません。私たちが来る前に、子どもたちは一人ひとりせんべいを作っていました。自分が形作ったせんべいを自分で焚火で焼いていきます。
-800x600.jpg)
ひっくり返すのがちょっと難しい
.jpg)
自分で作って焼いたせんべいの味は格別!
沸かしたお湯で入れたお茶と焚火で炒った秋の味覚を子どもたちに味わってもらいながら、火の恵みについて話をしました。①動物から身をまもる【安全】②暗い夜を照らす【明るさ】③体を温める【あたたかさ】④食べ物を加熱、調理する【おいしさ】など、火はいろいろなことに役立っていること、そしてその火をおこすために、森林が欠かせないことを伝えました。
-800x600.jpg)
秋の味覚をほおばる
-800x600.jpg)
活動の最後に記念撮影
調理をしたり、暖をとったり、照明として辺りを照らしたり…かつて火は、生きていくために、なくてはならないものでした。しかし、令和の今の時代はどうでしょうか? オール電化の家が増えたことで、火を見たことがない子どもたちが増えているともいいます。それに、自由に焚火やBBQができる場所も少なくなりました。このように人の生活が変わってきたことで、木を使う(切る)機会も減ってきました。木を使わない(切らない)と山は荒れてしまいます。今回の体験がそんな人と火の関係、森林や里山とのつながりを考えてもらうきっかけとしてもらえると嬉しいです。
以上報告は、どいっひこと土井早谷香でした。

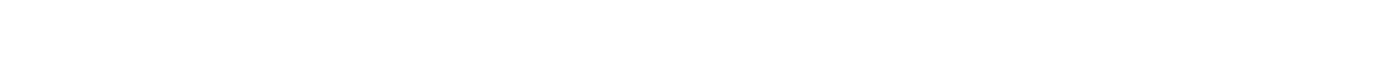
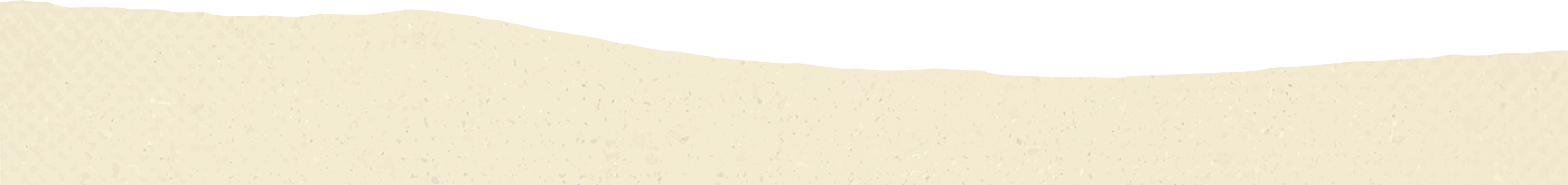

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)
Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529







