樹上作業のためのベーシックアーボリスト BAT-3B スパイククライミング
開催した日:
BAT-3Bは仕事上、どうしても樹木を断幹作業する必要があるプロフェッショナルの方用の講座です。
風倒木や雪折木、狭小地の庭木をやむなく伐採する場合、作業者の安全と作業の安全のため、スパイククライミングによるチェンソー断幹作業(SPUR (SPIKE) CLIMBING AND TREE REMOVAL/CHAINSAW)をします。そうした基本技術を学ぶ本講座は、BAT-3Aを受講後の方でかつチェンソー特別教育修了者のみが参加できるものです。
まず宇治田さんが参加者のギアをインスペクションしながら、使用するギアの特質も説明されました。

ギアインスペクションする宇治田マスタートレーナー
今回のBAT-3B講習は愛知県瀬戸市のアーボリスト・トレーニング研究所(ATI)から宇治田マスタートレーナー、近藤トレーナーに来て頂き、そのアシスタントとして元見さん、山崎さんにもお手伝い頂きました。
スパイククライミングに用いるスパイクには、長さが短いものと長いものがありますが、そのスパイクの長さは樹皮の厚みで使い分けます。使用する時にはスパイクを木部にまで刺すこと、地上を歩くときには脱ぐこと、スパイクの先端が命であるため平ヤスリで研ぐことなども説明されました。

スパイクの研ぎ方を説明する宇治田さん
この講座では作業者の安全を確保するためワイヤーコアランヤードを使用します。
ANSI規格(American National Standards Institute)では、グラブというランヤード調節ギアが付いているものしか使用が認められていません。このランヤードはワイヤーの表面をロープ繊維が覆っていますが、これはワイヤーの保護のための繊維です。このグラブ付きランヤードには「カット・アウェイ・ストラップ」を付けて装着すると、レスキュー時に便利です。
また6コイル・プルージック付のワイヤーコアランヤードでは扱いが簡単で、レスキューも容易ですが、ANSI規格(American National Standards Institute)で使用が認められていません。
どちらを使用するにせよ、ランヤードを両手で持って立木に摩擦がより多くかかるよう脇をしめて、スパイクを抜き刺しして少しずつクライミングします。スパイクとワイヤーコアランヤードを操作する手順では、片足ずつスパイクを動かして、両足が同じ高さに揃ってからワイヤーコアランヤードをフリップします。

スパイククライミングのデモをする宇治田さん
クライミングする時のランヤードやメインMRSロープの位置は、上から順に、①ワイヤーコアランヤード、②メインMRSロープ、③サブ・ランヤード の順にします。この順序にはどんな意味があるのかも、しっかり学びます。ワイヤーコアランヤードは必ず、腰より上の位置の幹に掛けることです。

参加者のクライミングをサポートする宇治田さん
とにかく繰り返し練習が重要なので、何度もランヤードの操作、スパイククライミング時の姿勢の保ち方、樹上での動き方を確認しました。

クライミング練習する参加者
樹木を上から断幹してくる場合、リギング・ブロックのためのセッティングはどうするのか。 チェンソーはどう操作するのか。 安全のための確認事項はたくさんあります。
チェンソーはストラップをつなぎ、サドルの真後ろに装着してクライミングします。樹上ではキックバックを勘案して、下刃操作を基本とします。

どのようなチェンソー操作をすれば良いのか確認する参加者
幹にランヤードやリギングロープなどを取り付ける順は上から
①ワイヤーコアランヤード、②MRSメインロープ、③リギングブロックスリング、④サブ・ランヤード の順とします。
特にリギングブロックは①カウヒッチ+ベターハーフ、②ティンバーヒッチの2種類の取り付け方がありますが、今回はカウヒッチ+ベターハーフ主体で繰り返し練習しました。

ロープやスリングの取り付位置を繰り返し練習する参加者
室内講義では「受け口」や「追い口」の作り方が、地上と樹上で違うことも学びました。樹上での受け口は重心との関係で直径にまで届くような深い「受け口」を作ること。「追い口」は「受け口」との会合点に合うようにすること。
樹上先端の梢を切るトップカットでは、コモン・ノッチやフンボルト・ノッチよりも、オープンフェイス・ノッチの方が、伐採後の立木の揺れが少ないこと。
またリギングにおけるハーフヒッチ & ランニングボウラインは、切り落とす丸太の上にランニングボウライン、丸太の真ん中と下側の受け口の中間にハーフヒッチを取り付けた方が、ロープがずれる心配がなく、また早い段階でロープにテンションがかかるので安全であること。
またチェンソーを止めて、最後に手鋸で追い切りする場合は、カーブソーよりもストレートソーの方が良いことも学びました。

室内での講義を受ける参加者
さて、2日目のスタートです。
早朝から幹にランヤードやリギングロープなどを取り付ける順の再確認です。 ①ワイヤーコアランヤード、②MRSメインロープ、③リギングブロックスリング、④サブ・ランヤード の順にできるか。
特にリギングブロックは①カウヒッチ+ベターハーフで取り付けられるか。そしてリギング時もペアとの合図はしっかりできているか。などなど繰り返し練習しました。

「low & slow」で昨日習った手順を再確認する参加者
ポータラップなどのロワリング・デバイスを取り付ける高さは、必ずグランドワーカーの腰の高さにすること。
樹上でハンドソーやチェンソーをどう取り廻すのか。断幹する幹にリギングロープを取り付けるのは①受け口をつくる前か②受け口をつくった後かなどいくつも復習項目があります。
もちろん受け口をつくってからハーフヒッチとランニング・ボウ・ラインによるリギングロープ設定が手順です。

樹上を想定した動きを確認する宇治田さんと近藤さん
チェンソーの持ち方、構え方は重要です。
地上で操作するのと違い、重いチェンソーをいかに疲れない持ち方ができるかが重要で、そのためには腕で持ち上げるのではなく、脇をしめて腕をわき腹につけて体全体でチェンソーを支えるイメージです。

チェンソーの持ち方を指導する宇治田さん
スパイクでクライミングする時に、ランヤード末端をスパイクで踏み抜いてしまう可能性もありますので、末端の処理も注意してもらいました。ランヤードはメインとするワイヤーコアランヤード、そしてバックアップとしてのランヤードの2本が必要です。
各自が練習し終えたので、本番の断幹処理の見本操作を宇治田さんが見せてくれました。
細いヒノキですがしっかりスパイクを利かせて、リギングロープをセッティングしてから、チェンソーと手鋸で断幹処理されました。


チェンソーと手鋸で断幹処理する宇治田さん
ところで使用しているスパイクのピンの利き具合は、ヒノキとアカマツでは全く違います。例えばアカマツではスパイクが良く利くため、ずり落ちることも少ないのですが、ヒノキでは滑ることしばしばです。
スパイクを打ち込む角度は良いか、樹上での自分の重心位置はどこかなども、しっかり身に着けないと安全な断幹作業が保証できません。

リギング操作を練習する参加者
受け口の作り方は①コモン・ノッチ、②フンボルト・ノッチ、③オープンフェイス・ノッチなどがあります。
ちなみにフンボルト・ノッチ(Humboldt notch)は日本語で「逆さ受け口」とも呼ばれますが、これはアメリカ西海岸では大径木伐採で利用される手法です。
この受け口の利点は、①大径木では受け口の破片が大き過ぎて取り除き難いため、フンボルトなら受け口から落ちやすい。②コモン・ノッチに比較して長めに木材が取れる。③伐倒木が倒れる過程で地面に落ちるため勢いを一度殺せ、結果として幹の破損を防げる可能性が高いのです。
さてさて、しかし樹上ではオープンフェイス・ノッチで半径分近くの深い受け口が多いことも念頭に置いて作業に励みました。適切の手順を踏んでいるかを宇治田さんが付き添いながら確認されていました。


チェンソーを利用する時、ワイヤーコアランヤードの掛け方がポイント。チェンソーの鋸断ラインと平行にしないといけません。
またリギングブロックを設置するための①ティンバーヒッチの特質、②カウヒッチ + ベターハーフの特質、つまり①ティンバーヒッチは比較的簡単い設置できるが、引っ張られる方向(力がかかる方向)が重要です。そしてカウヒッチは長いデッドアイスリングが必要ですが、安全性は高くなることも学びました。
そして最後に記念撮影して2日間の講座を終えたのです。

みんなで記念撮影
今回は参加者も少なく、濃密な講座を楽しく学べたことと思います。しかし重要なのは各自が地元に戻ってからも、安全で丁寧な作業を心掛けることなので、みなさん頑張って下さい。
以上報告、JIRIこと川尻秀樹でした。

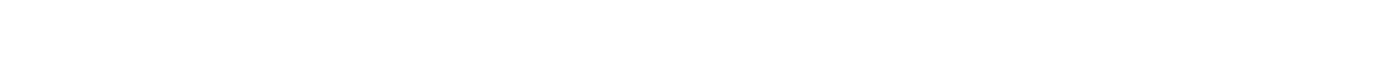
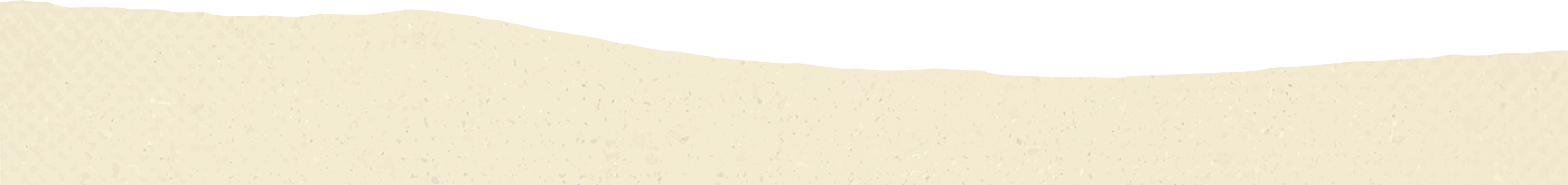

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)
Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529







