高山市清見小学校3年生、防災を兼ねた火起こし体験
開催した日:
岐阜県高山市の清見小学校、この学校からの依頼で『防災教育の一環で緊急時の火起こし体験をして欲しい』とのご依頼を受けて「morinos流の火起こし体験」をさせて頂きました。
最初にJIRIから清見小学校3年生のみなさんに、「火を起こすのに何が必要かグループに分かれて考えてください」と伝えて紙に書き出してもらいました。

最初に「火をつけるのに何が必要かを考える」
火起こし体験する3年生は柔軟な回答をいくつも考えてくれました。
「石、木、スギの葉、オイル(ガソリン)、摩擦、熱、酸素、布、薪、枯葉、炭、マッチ・・・」などなど、意外なほど正解が出てきました。

「火」に関しての項目を考える子どもたち
3グループのお子さんたちの回答は「酸素」、「摩擦」、「熱」などのポイントをしっかり押さえており、小学3年生は侮れない知識があることにも気づかされました。
また学校周辺で採取できるスギの葉は、緑色、橙色、褐色、黒色があるけれど、どれが燃えやすいのかも考えてもらい実際に体験してもらいました。

グループ毎に全員にシェアリングする子どもたち
たまたま火起こしに用いる「火錐」の名前が分からない例があったので、その絵を事例に指し示して、『木を擦って摩擦を起こし、木屑を作ってそれに熱をためて、火種をつくる』一連の作業について説明しました。

絵で表現したグループの絵で説明するJIRI
火起こしした種火を大きくするための小さな薪をつくります。morinosから持参した据え置き式の薪割り台に、太い薪を置いて木槌で叩いて細かくしてもらいます。
簡単に燃えるように、割ばし4本くらいの大きさにまで細かくしました。

燃料としての薪割
最初に道具を渡したら、子どもたち自身で火起こしのための道具をどう使えばよいのかを考えてもらいました。
最初はロープを使うこともなく、ただ火錐臼に棒を押し付けて手で回していた状態から、さまざま話し合って試行錯誤するうちに、徐々に理想の火起こしに近づいてきました。

5人で協力して火おこしするお子さんたち
お子さんたちは、掛け声を掛けたり、火錐棒の角度を考えたり、ロープを2重に掛けたり、挑戦する度に改良を重ねて諦めずにチャレンジし続けました。

火錐棒の主軸を真っ直ぐにすることが重要だと気づいたお子さんたち
火種が最初にできたグループでは、解した麻で火種を包み、少しずつ息を吹き込んで火を育てていました。すると一気に炎が上がって、麻が燃え始めたのです。

火種を麻に包んで息を吹きかけるお子さん
最初に着火に成功したグループは、まず焚火にあたっていました。
少し炎を育てたら、そこから燃えた薪を採取して、ケリーケトルのお湯を沸かすことに挑戦です。

着火に成功して火にあたるお子さんたち-
ケリーケトルは火を焚く火皿部分とお湯を沸かすポット&ロケットストーブの部分に分かれています。
その火皿で小さな焚火をして、その炎でお湯を沸かします。

着火した火をケリーケトルに移すお子さん
下の写真で左側がケリーケトルで、右側が焚火台です。
ケリーケトルについている緑色のキャップはシリコンでできたホィッスルで、お湯が沸くと「ピィー」と音が出ます。

お湯を沸かすケリーケトル(左)と焚火台(右)
ケリーケトルでお湯が沸くと、そのお湯で味噌汁を作りました。
防災上の備蓄品に賞味期限が近付いてきたフリーズドライの味噌汁があったそうなので、それを1つずつ提供してもらって飲みました。

ケリーケトルから即席みそ汁にお湯を注ぐお子さん
お昼ごはん前でお腹のすいたお子さんたち、「おいしい」を連発しながら味噌汁を食べてくれました。一生懸命火種を作り、着火させてお湯を沸かして口にした味噌汁は格別だったようです。

みそ汁に舌鼓を打つお子さん
味噌汁を飲んで一段落したお子さんたちは、スギの葉の燃え具合を確認していました。
前述のように集めたスギの葉は、緑色、橙色、褐色、黒色があったので、どれが燃えやすいのか自分たちで調べてもらいました。緑色や黒色のスギ葉は煙が多く、橙色のものが良く炎が上がることも分かったようです。

スギの葉の燃え方を確認するお子さん
最後に、JIRIから「今回、火起こしする時に成功するにはどうすれば良かったか」をグループで考えてもらい、それを紙に書いてもらいました。
その結果、お子さんたちからは、
協力する、息を合わせる、力を入れる、仲間と頑張る などの素晴らしい回答が返ってきました。

着火させるために何が必要だったかを発表するお子さんたち
清見小学校3年生のみなさん、3グループとも順調に着火できてお味噌汁も飲めて良かったです。
最後にこの活動には高山市緑化推進委員会の協力と、市役所の八賀さん、平瀬さん、清見町の塩谷さん、太田さんのお陰で実現できました。ありがとう御座いました。
以上報告、JIRIこと川尻秀樹でした。

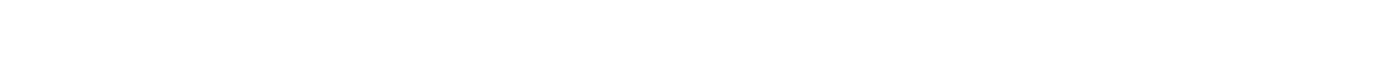
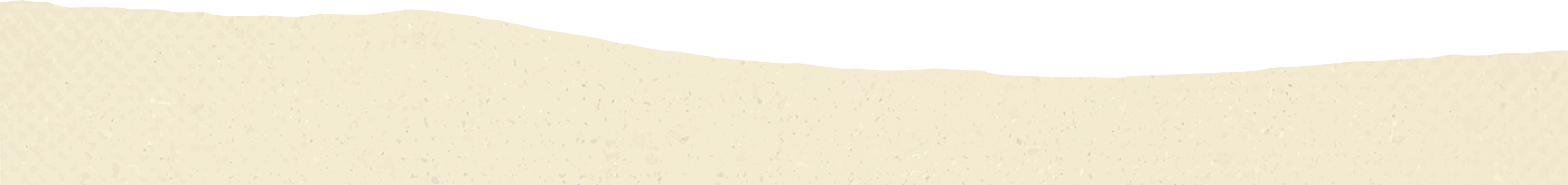

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)
Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529







