「森のじかん」が宮小学校へ!
開催した日:
高山市の宮小学校へ「森のじかん」の出前体験に行ってきました!高山の豊かな自然に囲まれた宮小学校の子どもたちと一緒に、森と水のつながり、そして土壌のはたらきについて楽しく活動してきたので、その様子を報告します。
学校に到着すると、子どもたちの元気な声が出迎えてくれました。まず高山名物のみたらしだんごをテーマにした「みたらしじゃんけん」によるアイスブレイキング。子どもたちの緊張もほぐれ、一気に笑顔に包まれました。

「みたらしじゃんけん」でウォーミングアップ
続いて、高山市一之宮町のシンボルである位山の源流から富山湾までの水の旅マップを見ながら、水がたどる長い道のりについて学びました。
この学校は富山湾近くの岩瀬小学校と交流があるそうです。川の上流地域と下流地域、それぞれの地域のことを知っていく機会があるといいですね。
私たちの暮らしに欠かせない「水」が、森の中でどのように育まれ、川となり、海へと流れ、また森へ還っていくのかを紙芝居でみた後は、いよいよ実験の時間です!
「森の土」と「河原の土」を実際に触って、その違いを比べてもらいました。なぜ、森の土と河原の土を比べるのでしょう? それは、森が持つ「緑のダム」としての役割を、五感と実験で感じてもらうためです。ふかふかで柔らかな森の土、硬くて小石の多い河原の土。子どもたちはその感触の違いに目を輝かせていました。

morinosから持ってきた「森の土」を触ってみる

学校裏の「河原の土」を掘って触る
この日のメインイベントは、ペットボトルろ過装置での実験です。4人1組のグループに分かれて、まずはろ過装置の制作。子どもたちは、ただ言われたとおりに作るのではなく、まさに「小さな研究者」。「この土は色が濃いから、もっとたくさん入れよう」「こっちの砂利と、あっちの砂、どっちがいいかな?」と、土の色や質感の違いに気づき、量や種類を相談しながら、自分たちなりの森と河原の土壌の層を考えていました。子どもたちは、思い思いの石、砂利、砂、草、土などを入れ、ろ過装置を作ることを心から楽しんでいるようでした。

自分たちが考えた順番で石や砂、土をろ過装置につめていく
「森の土」と「河原の土」、2種類のろ過装置に泥水を流してみると、その違いは一目瞭然です。森の土の層を通った水は、ゆっくりと時間をかけてろ過され、透明になっていきます。一方、河原の土を通った水は、あっという間に下に流れ落ちていきました。

実際に泥水を流してみる
森の土では泥水が薄くなり白っぽくなりました。河原の土では濁った色のままでした。

それぞれの結果はこのとおり!
最後に班ごとに500mlの水を一気にろ過装置に流し込みました。
森の土の層のろ過装置はスポンジのように水を吸収し、ゆっくりと下の容器に水を送り出していました。一方、砂利や砂でできた河原の土のろ過装置は、水を通すばかりでほとんど溜めることができません。この違いから、森の土が保水力を通じて、急な大雨による川の氾濫などを防いでくれていることがよく分かります。

森の土と河原の土、その違いは一目瞭然!
今回の出前授業を終え、子どもたちからはたくさんの素敵な感想が聞かれました。
「次やるときはもっときれいにろ過できるようになりたい」
「森って大事なんだということに気づいた」
「森の土と川の土(砂)をさわってみて、全然違うことに驚いた」
今回の授業は、子どもたちが自分たちの住む町の自然が宝物だと感じ、将来にわたって誇りに思ってほしいという、宮小学校の先生方の願いから実現しました。これから森林組合の皆さんから森について学ぶ機会があるそうなので、今回の体験がその入り口になれば嬉しいです。宮小学校の皆さん、楽しい時間を本当にありがとうございました!
以上報告は、どいっひこと土井早谷香でした。

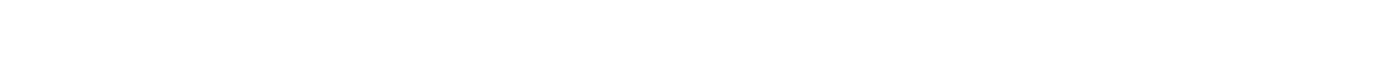
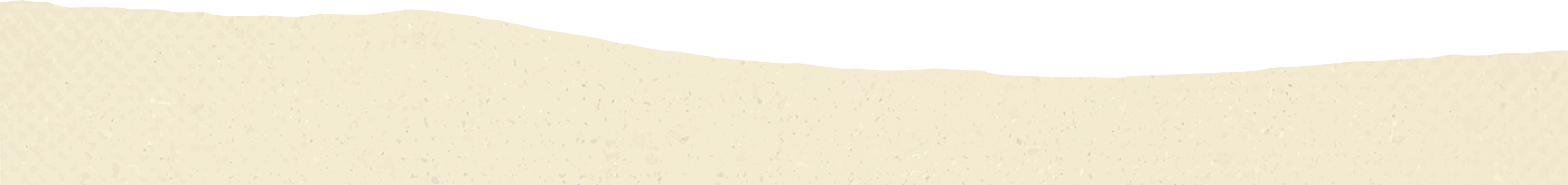

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)
Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529







